私は数年前に弁理士付記試験を受験し、1度の受験で合格しました。弁理士試験とは異なり特に週末勉強漬けなどの対策をすることはせずに効率的に合格できました。これから弁理士付記試験を受験する方にとって役立つことがあればと思い、情報共有したいと思います。
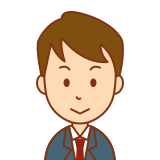
付記試験って何?弁理士試験と違うの?
弁理士付記試験て何?
弁理士付記試験は、正式には特定侵害訴訟代理付記試験という試験で、弁理士でないと受けられません。そして試験に合格すると弁理士よりも、代理できる業務範囲が広がります。具体的には一定範囲の知財に関する侵害訴訟の訴訟代理人になれます。
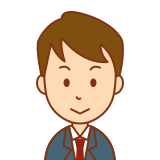
へぇー。で、とったほうがいいの?
弁理士付記試験に合格するメリットは?
まずデメリットですが、ある程度の費用がかかるのと、一定の勉強時間が必要であるのがデメリットです。費用は約30万円で内訳は以下の通りです。
- 民法・民事訴訟法に関する基礎研修(総合コース): 86,400円(税・テキスト代込み)
- 能力担保研修: 200,000円(各種テキスト、副読本代を含む。消費税は非課税)
- 受験手数料: 7,200円(特許印紙にて納付)
- 登録費用: 6,800円
※このうち、上記1の費用は、大学、専門学校等で民法・民事訴訟法の知識を習得している場合は不要です。
上記の通りデメリットはあるものの、私はこのデメリットを上回るメリットが十分にあると思います。以下が主なメリットです。
- 多くの弁理士は出願・中間処理がメインのため、実際にこの資格を使って訴訟代理人になる方は少数と思います。しかし、だからこそ、この試験に向けた学習の中で訴訟関連の実務の知識を増やせること自体がメリットです。訴状・答弁書、裁判例に多く触れる機会があり、自然と訴訟関連の知識が増えていきます。
- 弁理士の明細書作成業務においては、将来の権利活用、訴訟も踏まえてドラフトされると思いますが、そのときに役立つ基本的な知識が身に付くのもメリットです。
- 名刺に「特定侵害訴訟代理付記」と書けるのも小さなメリットの一つと思います。
要するに明細書作成業務に役立ちますし、訴訟を経験するチャンスも皆無ではないと思いますので、この試験の対策をすること、資格を得ることには十分メリットがあると思います。
なお民法・民事訴訟法に関する基礎研修を受けることが受験資格の要件になっています。この研修は非常に有益で、特に講師の弁護士 村西先生が非常に説明が分かりやすく、この基礎研修で学ぶことにも意義があると思います。私は、この基礎研修を受けられたことが一番価値があったと思います。ちなみに弁理士の継続研修の単位にもなります。他の継続研修と比較してもその中身は突出して充実しています。
試験の形式・合格率は?
論文式の筆記試験です。年1回開催(10月中旬から12月下旬の土曜日又は日曜日のいずれかに、1日間で実施)されます。前半3時間(民法・民訴・特実)、後半3時間(民法・民訴・意商)の合計6時間の試験です。試験の詳細は以下をご確認下さい。
以下の統計データによると、合格率は50%超程度です。弁理士試験と比較すると相当高いです。ただ受験しているのが全員弁理士である点にはご留意下さい。弁理士試験合格者のうち半分程度が受かるレベルです。
具体的な試験対策は?
私は週末の時間を確保することができなかったため、主にスキマ時間を利用して対策しました。学習に利用した書籍は以下です。
- 弁理士のための民法〔第3版〕弁護士 村西 大作 (日本弁理士会 研修所)
- 弁理士のための民事訴訟法〔第3版〕弁護士 村西 大作 (日本弁理士会 研修所)
- 能力担保研修のテキスト
- 特定侵害訴訟代理業務試験過去問から学ぶ 知財訴訟の訴状・答弁書の実例 平成24年度〜平成28年度 付記試験過去問・山の手総合研究所模試 問題・模範解答・解説レジュメ 弁護士 横井 康真 ((株)山の手総合研究所)
- 特定侵害訴訟代理業務試験過去問から学ぶ 知財訴訟の訴状・答弁書の書き方 <付記試験過去問 問題・模範解答付> [集約版] 弁護士 横井 康真 ((株)山の手総合研究所)
- <新訂> 民法概説(四訂版) 司法協会
- 民事訴訟法講義案(三訂版) 司法協会
上記の1−2の書籍(基礎研修のテキスト)はとても役立ちます。これを繰り返し学習すれば、民法・民訴の試験対策の知識量は必要十分に思います。
民法・民事訴訟法は、弁理士試験では出てこない用語が多数登場します。これらをしっかりと頭に入れておく必要があります。私は上記1-2の書籍に登場する法律用語は、ankiwebを使って徹底的に暗記しました。ankiwebは私は日常的に使っていて他の資格試験でも活用しています。以下の記事をご参照下さい。
また上記3の能力担保研修のテキストも役に立ちます。これも数回通読することをオススメします。
過去問を見ておくことも重要です。私はインターネットで上記4-5の書籍を購入して、この過去問を繰り返し解きました。ただ、論文を書く練習はそれほど本格的にはやりませんでした。弁理士試験のときは答練・模擬試験等を受験しましたが、付記試験については、週末に勉強時間を取らないと決めていましたし、模試も週末でしたので必然的に一切受けませんでした。ただある程度過去問のパターンも決まっていますし、それほど練習する必要はないと思います。むしろ知識をしっかりインプットしておけば、十分に合格ラインに届きます。
能力担保研修時に推奨図書とされている上記6−7の書籍はざっと関連する部分数ページを参考程度に読んだ程度で、あまり使っていません。試験対策としては購入しなくても問題ないと思います。
対策しなくてもよいこと
弁理士試験とは異なり、以下の対策は不要と思います。受験者は皆弁理士なので、他の方の合格体験記を見ると、弁理士試験の対策のように徹底的に勉強している方が多くいらっしゃいます。ただ経験してみればわかると思いますがそこまでの対策はしなくても大丈夫です。弁理士試験を突破できた人にとっては、きちんと集中して学習すれば難しい試験ではないと思います。普段の生活の中に学習時間を毎日取り入れることができる弁理士であれば、十分合格できる試験です。
- 模擬試験
- 論文を書く練習
- 基本書等による発展的な学習
おわりに
ここまで読んで頂きありがとうございます。これから受験を考えている方、この試験勉強が大変だと思って躊躇する必要は全くありません。弁理士試験とは異なり、週末一切勉強しなくても合格可能です。キャリアアップを目指すのであれば、上述の通りメリットもあると思いますので、ぜひチャレンジすることをおすすめします。このブログ記事がお役に立つと幸いです。





コメント